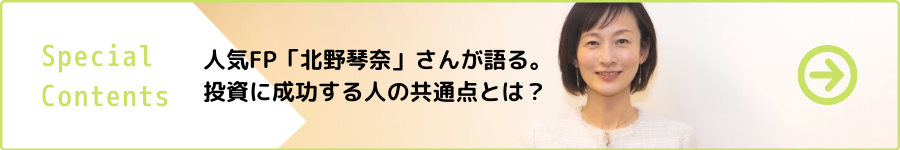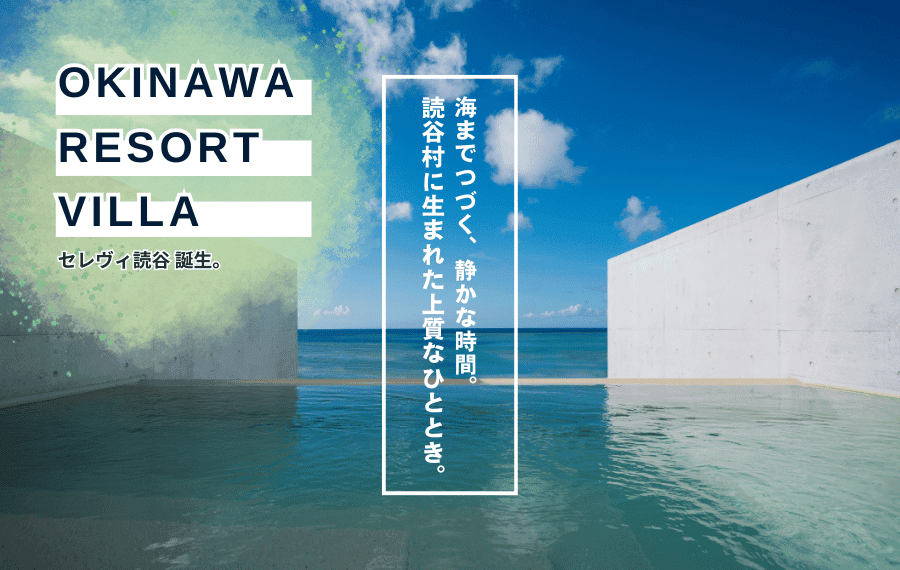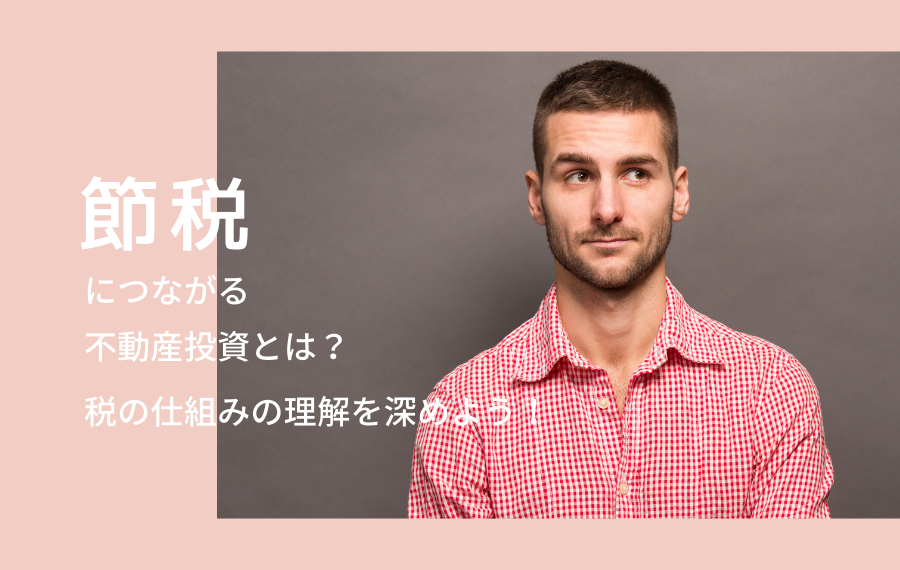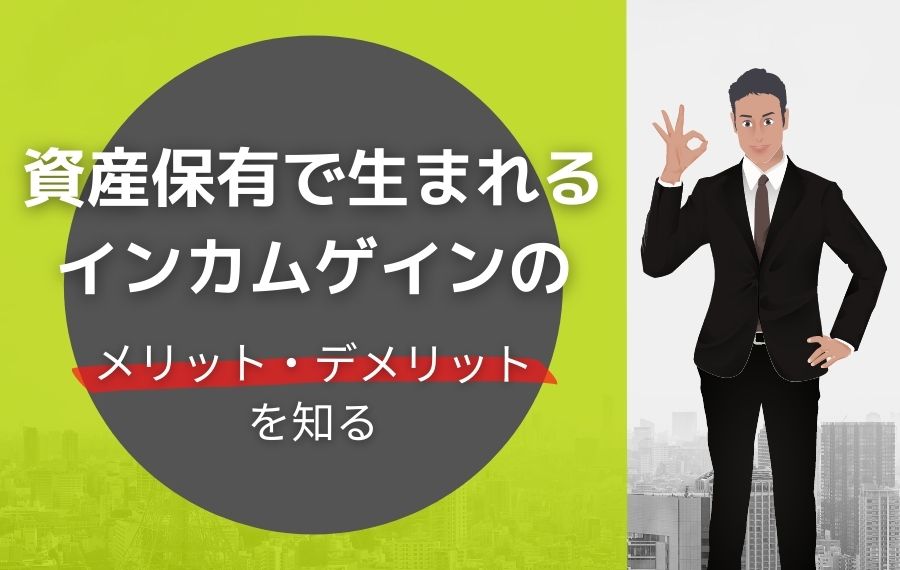BLOGブログ
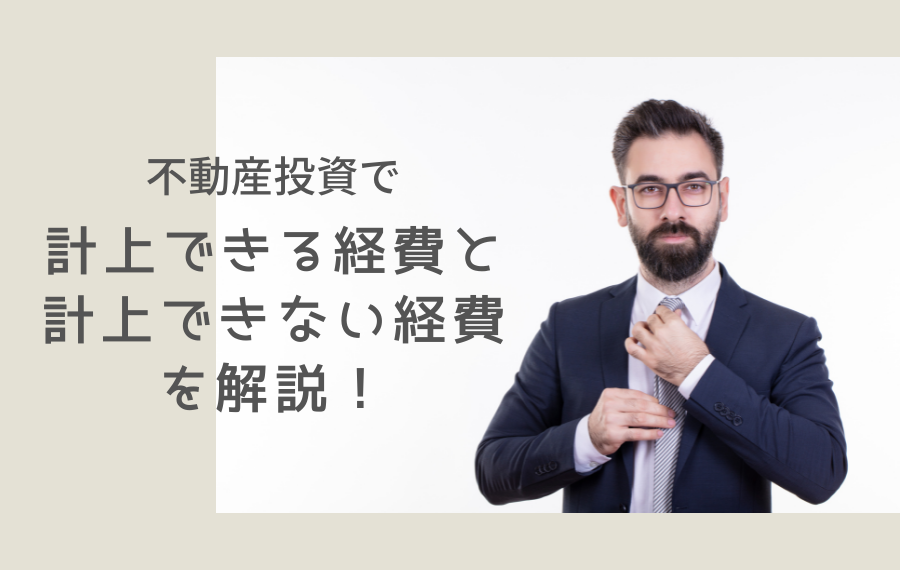
不動産投資で計上できる経費と計上できない経費を解説!
更新日 2022年5月16日
不動産投資というと家賃収入など利益にばかり目が行きがちですが、収入が発生するということは同時に納税の義務が生ずることを意味します。
“不動産投資は税金との戦い”ともいわれるほど、所得税をはじめ様々な税負担がのしかかります。
仮に、物件内容や入居率などが同一条件の物件があったとしたとしても、税負担の度合いで利益に差が出てしまうことがあるのです。
そのため、適切な範囲で支出を経費として計上し、利益を圧縮することにつながれば、支払う税金が少なくなり収益の向上に貢献します。
経費を正しく計上することは節税の第一歩です。
しかし、不動産投資でどこまでが経費に計上できるかわからないといった人も多いでしょう。
今回は、不動産投資で認められる経費、認められない経費について詳しくご説明します。
- 不動産投資を始めたい
- 不動産投資で計上できる経費を知りたい
こちらの記事もおすすめです
✅不動産の固定資産税はいくらかかる?
✅節税につながる不動産投資とは?
✅固定資産税評価額の調べ方や税金の計算方法について解説
不動産投資の経費の考え方とは
不動産投資は、家賃収入という一定の売上があるのが魅力である一方、他の事業のように人件費など高額なランニングコストが発生しにくいため、しっかりと節税対策をしないと高額な課税をされるリスクがあります。
経費として計上できるものが何なのか、しっかり頭の中に入れておきたいものです。
不動産投資で得られた収入(=不動産所得)は、
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
と定義されます。
不動産所得を導き出すには、総収入金額と必要経費をしっかり把握することが肝心です。
ちなみに、総収入金額には、家賃収入のほか礼金、更新料、管理費、共益費などが含まれます。
一方、必要経費は「家賃収入を得るために支払った費用」を指します。
必要経費に計上できるものは多岐にわたるので、個別の内容は以下に紹介していきます。
経費と税金の関係性
不動産を購入したり、保有したりすることでかかる税金は、
・不動産の購入 不動産取得税、印紙税、登録免許税
・不動産の保有 固定資産税、都市計画税
で、いずれも経費の対象です。
ちなみに、固定資産税と都市計画税の計算は以下のようになります。
税額の算出に際しては、標準課税(固定資産税評価額)といわれる保有している土地・建物の金額(税率をかける金額)を用いることで、下記の計算式で求められます。
固定資産税の税額=課税標準×1.4%
都市計画税の税額=課税標準×0.3%
なお、固定資産税評価額は、購入価額の5~6割が一般的です。
また、土地については「小規模住宅用地」として、課税標準が6分の1(200㎡まで)に、建物については新築の場合は減免措置があります。
固定資産税と都市計画税を合算すると、上記のように税率は1.7%になりますが、実際の税額は「購入金額の0.5%前後」になるのが一般的といわれます。
ただし、実際に税額を自分で計算する必要はなく、市町村から届く書面に記載された税額を納付するだけです。
そのため、固定資産税と都市計画税は決められた税額を税務署へ納付するのが原則で、節税の対象にはなりません。
そのほか、家賃収入から経費を差し引いた金額(利益)には、所得税や住民税がかかります。
不動産投資で経費にできるものとは

各種税金
不動産投資で課税される各種税金も必要経費として計上が可能です。
主なものは、不動産を購入した際にかかる不動産取得税、印紙税、登録免許税。
不動産を保有している期間は、毎年かかる固定資産税、都市計画税があります。
保険料
建物にかかる損害保険のことを指します。
不動産投資においては、購入に際して火災保険や地震保険に加入することが一般的ですが、これらの保険料は経費に計上できます。
また、近年は孤独死保険など新たな保険が登場していますが、物件の所有者が負担する保険料は経費となります。
減価償却費
建物・部屋の取得費用は、1度に経費として計上するのでなく、減価償却費として毎年経費に計上します。
建物(減価償却資産)には、法定耐用年数といって法定上定められた使用可能な年数があります。
建物の取得費用を耐用年数で割り、その金額を毎年経費に計上することを減価償却といいます。
そのため、実際の出費がない場合でも経費に計上できることから、帳簿上の利益を減らせるため、節税対策になります。
建物(新築・住宅用)別の法定耐用年数は以下のようになっています。
・木造の建物=22年
・鉄骨構造の建物=19年、27年、34年(構造材料により異なる)
・RC造の建物=47年
なお、実際の減価償却期間は、上記の法定耐用年数と築年数をもとに計算します。
修繕費・管理費
賃貸物件では、建物が傷んだり、設備が故障したりすれば、原則、物件の所有者が修繕をします。
また、建物は時間の経過とともに必ず老朽化しますし、入居者の使用による劣化も。
不動産収入を得るためには、部屋の機能を原状回復することが必要ですから、これは修繕費として経費に計上できます。
代表的な修繕費には、部屋のクリーニング代・壁紙の交換費用・給湯器やエアコンなどの設備交換費用などが挙げられます。
また、マンションの場合は、管理費の名目で共用部分の清掃やメンテナンスの費用、大規模修繕のための費用(修繕積立金)などを毎月支払いますが、これらも修繕費として計上可能です。
ただし、最新型の給湯器への変更や間取りの変更など設備機能を向上させる費用(設備投資)は、修繕費として一括で経費計上ができません。
この場合は減価償却の対象となり、それぞれの設備の法定耐用年数に従って減価償却費として計上します。
管理委託料
所有物件の家賃徴収や清掃、トラブル解決といった業務を不動産管理会社に手数料を払って依頼している場合は、不動産収入を得るために必要な経費として認められます。
専門家への報酬金
物件購入の際に不動産登記の手続きを司法書士へ依頼したり、確定申告の代行や税金上のアドバイスを目的に税理士と契約したりした場合など、専門家に業務を依頼した場合は、その報酬を必要経費として計上できます。
広告宣伝費
入居者を募集するときにかかる費用は経費になります。
不動産広告の掲載料や管理会社、仲介会社への広告宣伝費も認められます。
また、賃貸の仲介会社へ支払う仲介手数料も経費に計上できます。
ローン金利
金融機関から融資を受けて物件を購入した場合、毎月決まった額を返済していきますが、そのうち何割かは借入金の元本ではなく、ローンの金利です。
物件購入の費用は減価償却費となりますが、このローン金利は毎月かかる経費として計上できます。
ただし、建物部分の金利はすべて経費になりますが、土地部分の金利には上限があります。
旅費・宿泊費
不動産投資に関連する旅費、宿泊費には、以下のようなものが考えられます。
・物件の下見や調査
・購入や物件の管理のための現地訪問
・交渉や契約のために不動産会社や金融機関への訪問
といった場合に、移動に際しての公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代、駐車場代、遠隔地の場合はホテルの宿泊費などが計上可能です。
交際費
交際費とは、接待、供応、慰安、贈答、その他これに類するものと、意義が定められています。
不動産投資の場合は、不動産会社や管理会社の担当者と食事をした際の飲食代は経費となります。
また、慶弔費なども該当します。
なお、喫茶店で打ち合わせをした場合の飲み物代などは、会議費として計上できます。
いずれも、不動産投資に関わる出費であることが証明できる書類やデータが必要で、レシートや領収書とともに、面会した日取りや場所などを記録しておくようにしましょう。
自動車の関連費
不動産投資の仕事上で自動車が必要であれば、車両の購入代金のほか、車検などのメンテナンス費用、自動車税、保険料といった維持費も経費として計上可能です。
ただし、自家用車を不動産投資にも使用する場合は、日常生活に使った分は家事按分をして、不動産投資で使った分だけを費用計上します。
なお、交通違反による罰金や反則金は経費に計上できませんが、レッカー代金は経費として認められます。
通信費
不動産会社や管理会社との連絡や情報収集のために使った通信費用も経費に計上できます。
具体的には、
・スマホ(携帯電話)やパソコンの購入代金
・携帯電話の使用料
・インターネットプロバイダーに支払う料金
・不動産投資に使用するアプリなどの購入代金
などです。
ただし、自動車と同様に、私用でも同じものを使用している場合は、家事按分をする必要があります。
情報収集費
不動産投資をする上で必要な情報収集や勉強のための費用も経費に計上できます。
具体的には、
・新聞や書籍の購入費
・セミナー代金
・コンサルティング費用
などです。
ただし、一見関係がありそうですが、資格取得費用は不動産関連であっても認められません。
不動産投資で経費にできないものとは

そうならないためにも、具体的にNG例を紹介します。
投資と関連性がない出費❌
不動産投資の経費に計上できるのは、あくまでも「不動産投資によって収入を得るための経費」です。
言い換えれば、不動産という資産を運用し、管理するために必要な費用です。
当然ながら、所有する物件に関係のない旅行の費用や食費などは経費にはなりません。
なかでも飲食費については、個人事業主であれば食費はすべて経費にできる、といった誤解が流布していますが、プライベートの食事代は認められません。
住民税・所得税・法人税❌
住民税や所得税は国民すべてに納税義務があり、経費とは認められません。
不動産投資、不動産の所有に関係なく発生するものです。
スーツ購入費❌
不動産投資では、不動産会社や管理会社、金融機関の担当者に会う際、スーツを着用する必要が発生する場合も多くあります。
また、腕時計やカバンなどの持ち物に気を使うのもビジネスマナーでしょう。
しかし、仕事用のスーツや腕時計、服飾品などは経費として計上できないと考えられています。
これは、プライベートでも区別なく使用できることが、経費にできないと判断される根拠です。
スポーツジムの会費❌(条件付きで可能な場合も)
基本的に、スポーツジムの会費は経費に計上できません。
これは、不動産投資の場合、個人事業主に福利厚生が認められていないためです。
ただし、法人として経営を行い、家族以外にも従業員がいる場合は、福利厚生費として経費計上できる場合があります。
反則金・罰金❌
自動車関連費用の経費に思われますが、スピード違反や駐車違反などの反則金や罰金は経費として認められません。
前述しましたが、レッカー代金については経費として認められます。
資格取得費❌
不動産関連の資格には、宅地建物取引士(宅建士)、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士などがあります。
しかし、いずれの資格取得費用も経費としては認められていません。
理由は、あくまで個人のスキルアップのための費用と見なされるからです。
条件によっては経費にできるものとは
同じような支出であっても、条件によって経費としての扱いが異なることもあるのです。
こうした場合は、判断を間違えないようにしましょう。
修繕費
物件の工事において、その工事費を「資本的支出」にするのか、「修繕費」にするのかは、判断に迷う代表的なものです。
「資本的支出」とは、その物件の資産価値を上げるための工事などの費用です。
この場合は複数年にわたる減価償却とします。
「修繕費」とは、原状回復するための工事等の費用です。
この場合は、工事をした年に一括で経費として計上できます。
いずれも、物件の工事をしたという点では同じです。
では、いったいどこに違いがあるのでしょう。
わかりやすい事例を挙げて説明します。
資本的支出とみなされる例
・外壁等をモルタル塗装からタイル張りへと変更する
・室内の壁紙を高品質のものにグレードアップする
・ガス給湯器を、最新型の追い焚き付きオートバスにする
以上のように、現状よりも物件のグレードをアップすることを目的とした工事です。
これらの資本的支出は、国税庁が定める耐用年数にしたがって、減価償却費として計上します。
修繕費とみなされる例
・グレード変更を伴わない定期的な外壁塗装
・同程度のグレードの壁紙に張り替える
・現状のガス給湯器と同型もしくは同程度の機能の機種に取り替え
これらはあくまで原状復帰であり、修繕費として計上できます。
したがって、支出のあった年に一括で経費に計上できます。
工事には当然ながら出費が伴います。
できれば修繕費として一括で経費として計上し、節税につなげたいところです。
しかし、工事内容によっては修繕費としての一括の経費計上を税務署で認められない場合もあります。
工事内容をよく吟味して、正確に申告することが肝心です。
家族への給与
家族の給与が経費として認められるには、青色申告(後述)をする必要があります。
ただし、不動産投資が事業規模でないと青色申告するのは難しいでしょう。
仮に青色申告者となっても、青色専従者給与の額を大きくすることは、税務で否認されたり、税務調査を呼び込んだりするリスクを伴います。
給与額と仕事の内容に乖離がないかどうか、よく検討する必要があります。
節税に効果的な費用と効果的でない費用
不動産投資にまつわる経費は、多岐にわたります。
しかし、どの項目も経費の額を最大化すればいいわけではありません。
節税のためには、効果的な経費計上が重要です。
経費には以下の2つのパターンがあることを覚えておきましょう。
・最大化すべき経費……減価償却費
・最小限に抑えるべき経費……その他の経費
減価償却費は、実際の出費を伴わない経費のため、最大化を目指すべき経費です。
減価償却費を最大化させるには、多くの減価償却費が出る物件を選ぶことが重要になります。
ただし、減価償却費として経費を計上していくと、物件を売却する際に減価償却した分だけで物件の簿価が低くなっており、最終的に利益が出やすくなることを念頭に置いておく必要があります。
そこで、売却益にかかる所得税と物件を保有しているときに節税できる所得税の税率を比較して、減価償却費を最大化するべきかどうか確認をすることが肝心です。
年収が低い場合(目安は年収1,200万円未満)は、メリットが少ない場合もあるので、注意が必要です。
一方、減価償却費以外の経費は、必要最小限に抑えるべきです。
これらの経費は、基本的に経費と同じ額が出費となるからです。
仮に、経費に計上するために出費を多くしても、確定申告で所得税の還付として戻ってくる額よりも、実際の出費が上回っていては意味がありません。
経費の全体像を予測する
経費の正確な数字は、じっさいに不動産を購入してからでないと確定できませんが、不動産投資の成功率を高めるためにも予測を立てることは重要です。
なぜならば、思ったよりも経費がかからなかった場合は、節税効果が低くなります。
反対に突発的な修理などで出費がかさむと経費がかかりすぎたことになり、最悪手元資金がショートしてしまうこともありえます。
いずれの事態も織り込んで、経費を予測することが大切です。
経費のうち、ローンの金利や減価償却費などは、不動産会社が作成する投資シミュレーションに入っていることが多い項目ですし、金利や税金、管理委託料、保険料、専門家への報酬などは、ある程度正確に予測ができます。
また、仲介手数料や広告宣伝費、修繕費などは、空き室や平均入居率などをベースにシミュレーションできます。
そのほか、通信費や交通費、自動車関連の費用、交際費なども、個人の事情に合わせてある程度は予想できるでしょう。
確定申告なら青色申告でさらに節税
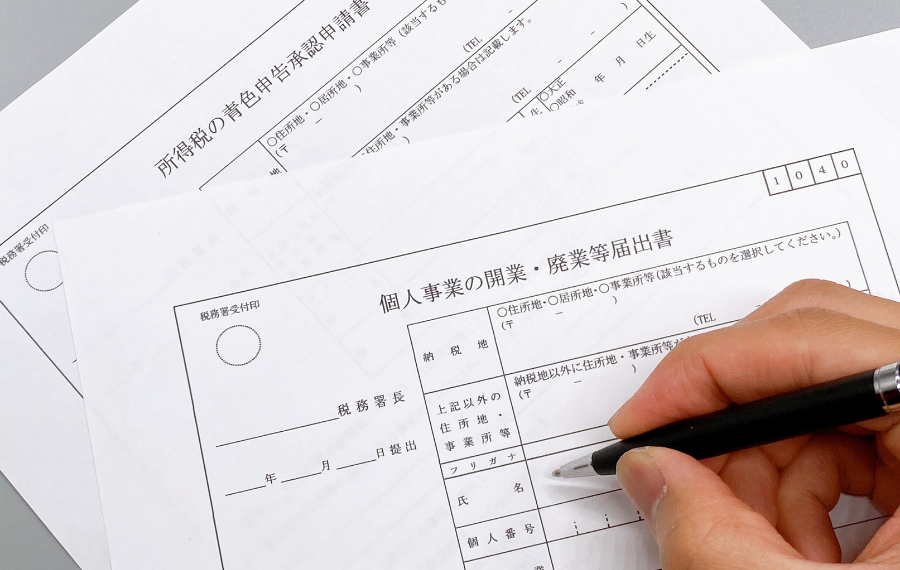
確定申告は通常「白色申告」ですが、税制上の優遇措置を受けられる「青色申告」も検討するのも1つの選択肢です。
青色申告のメリットは、主に「青色申告特別控除」と「純損失の繰越控除」の2つ。
「青色申告特別控除」は、所得から10万円を差し引くことができます。
また、物件を5棟もしくは10部屋以上の物件を所有する場合には、事業規模となるため、65万円の控除が受けられます。
「純損失の繰越控除」では、ある年に収益が赤字になった場合、翌年以降3年間に渡って赤字を繰り越すことができます。
これにより、赤字の翌年に大きく黒字が出たとしても、繰り越した赤字額で相殺して課税金額を抑えることが可能です。
なお、青色申告を行う場合は、事前に開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出し、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳することが前提となります。
まとめ|不動産投資の経費は収益に与える影響が大きい
多岐にわたる経費項目は、不動産投資の収益に大きな影響を与えることがおわかりいただけたと思います。
経費に計上できるか、計上できないのかを正確に判断できるようになることは、節税上の大切な知識であり、投資の効率を上げるツールでもあります。
また、不動産購入に際して経費の全体像を予測できることは、不動産投資の成功の確率を高めることにつながります。
経費に関する認識を改め、今一度、ご自身の経費の内実をチェックされてみてはいかがでしょうか。
もっと手軽に、もっと身近に!1万円から始められる次世代の不動産クラウドファンディング「利回り不動産」
多額の資金が必要となる不動産物件を小口化させて、短期間で投資ができる不動産クラウドファンディング。
「将来のために資産形成をしたい」「少額で不動産投資を始めたい」「中長期的な資産形成に挑戦したい」
「利回り不動産」では、運用実績が豊富な投資のプロが、みなさまからの資金で一定の期間不動産を運用し、家賃収入や売却益などを還元。
1万円から投資ができ、不動産投資に申し込みから分配金の受け取りまで、すべてインターネット上で行うことができます。
RIMAWARIBLOG運営元情報

- RIMAWARIBLOG編集責任者
- 「利回り不動産」が提供する「RIMAWARIBLOG」ではサービス利用者へ向けた企画情報の発信に加え、各分野の専門家の監修・協力を得て、不動産投資や資産形成をはじめたいと考えている読者に向けて、親切で役に立つ情報を発信しています。